Q23 対象者を現在の生活習慣から喫煙群と非喫煙群とに分け、喫煙に起因する将来の 脳血管障害の発生を明らかにする疫学研究法はどれか。
- 横断研究
- 記述的研究
- コホート研究
- 症例対照研究
- 無作為化比較試験
※ 下にスクロールしても、
「23 対象者を現在の生活習慣から喫煙群と非喫煙群とに分け、喫煙に起因する将来の 脳血管障害の発生を明らかにする疫学研究法はどれか。 」
の解答を確認できます。
「Q23 対象者を現…」の解答
3
スポンサーリンク
正解だった方は、他の問題もどうぞ。
この過去問は、以下の国試の設問の1つです。下のリンク先のページから全問題をご確認いただけます。
この過去問の前後の問題はこちら ▼
« 前の問題
Q22 成人に対する一次救命措置で正しいのはどれか。
» 次の問題
Q24 嫌気的代謝の過程で生成される物質はどれか。
ご質問も受け付けています!
「Q23 対象者を現在の生活習慣から喫煙群と非喫煙群とに分け、喫煙に起因する将来の 脳血管障害の発生を明らかにする疫学研究法はどれか。」こちらの国試問題(過去問)について、疑問はありませんか?
分からない事・あやふやな事はそのままにせず、ちゃんと解決しましょう。以下のフォームから質問する事ができます。「Q23 対象者を現在の生活習慣か……」に関連するページへのリンク依頼フォーム
国試1問あたりに対して、紹介記事は3記事程度を想定しています。問題によっては、リンク依頼フォームを設けていない場合もあります。予めご了承下さい。
更新日:
コメント解説




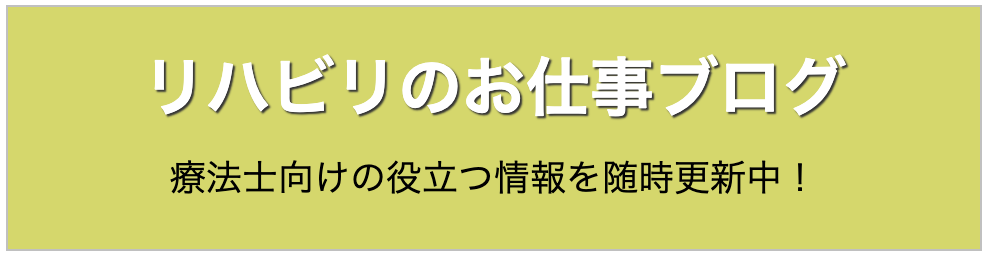


国試問題「第52回理学療法士国試【午前】問23 対象者を現在の生活習慣から喫煙群と非喫煙群とに分け、喫煙に起因する将来の 脳血管障害の発生を明らかにする疫学研究法はどれか。」について、1件のコメント解説
スポンサーリンク
コホート研究とは、縦断研究とも呼ばれ、特定の要因に曝露した集団Aと曝露していない集団Bを一定期間追跡し、研究対象となる疾病の罹患率や、症状の改善・悪化の有無などを比較することで、要因と疾病発生(症状の改善・悪化)の関連を調べる観察的研究の事を言います。
(経過を追うので縦断研究となります。)
問題文では、
要因=喫煙
疾病発生=脳血管障害
となっています。
「一定期間」については明記されていませんが、「将来の」という記述を見れば、コホート研究である事が理解できると思います。少なくとも横断研究という判断をする事はないはずです。
無作為化比較試験もコホート研究の一種とみなすこともできますが、複数の患者集団に、それぞれ異なる治療法(介入)をランダムに割り当てるという点で異なります。
問題文では、「無作為」という点に触れていない事や、「異なる介入」を行なってはいないため、コホート研究と判断する事ができます。
介入を行った上で、その差を比較する場合は、比較試験となります。