Q52 体表から触知できるのはどれか。2つ選べ。
- 歯突起
- 結節間溝
- 胸骨角
- 顆間隆起
- 舟状骨粗面
※ 下にスクロールしても、
「52 体表から触知できるのはどれか。2つ選べ。 」
の解答を確認できます。
「Q52 体表から触…」の解答
3と5
スポンサーリンク
正解だった方は、他の問題もどうぞ。
この過去問は、以下の国試の設問の1つです。下のリンク先のページから全問題をご確認いただけます。
この過去問の前後の問題はこちら ▼
« 前の問題
Q51 外胚葉から発生するのはどれか。
» 次の問題
Q53 回旋筋腱板を構成する筋はどれか。2つ選べ。
ご質問も受け付けています!
「Q52 体表から触知できるのはどれか。2つ選べ。」こちらの国試問題(過去問)について、疑問はありませんか?
分からない事・あやふやな事はそのままにせず、ちゃんと解決しましょう。以下のフォームから質問する事ができます。「Q52 体表から触知できるのはど……」に関連するページへのリンク依頼フォーム
国試1問あたりに対して、紹介記事は3記事程度を想定しています。問題によっては、リンク依頼フォームを設けていない場合もあります。予めご了承下さい。
更新日:
コメント解説





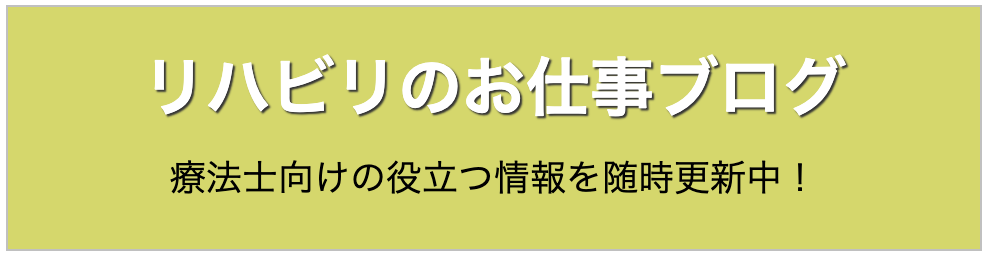


国試問題「第52回作業療法士国試【午前】問52 体表から触知できるのはどれか。2つ選べ。」について、2件のコメント解説
スポンサーリンク
[胸骨角]
胸骨柄と胸骨体の結合部。胸骨柄が胸骨体に対しわずかに後傾しているため、結合部で凸状の部分が触知可能である。
ちなみにこの胸骨柄と胸骨体合わさることで側面に第2肋骨切痕が形成される。
[舟状骨粗面]
舟状骨(足根骨)の内側にある隆起部。内果の前下方2cmくらいのところで体表から触知可能である。また、足部内側縦アーチ計測の際に指標として多く用いられている。
[歯突起]
第2頸椎の椎体から上方へ突出している部分。深部にあるため触知は難しい。
この歯突起は第1頸椎と関節をつくり、主に回旋運動の軸となる。そのため第2頸椎は軸椎とも呼ばれる。ちなみにこの歯突起は元々第1頸椎の椎体であったものが、第2頸椎の椎体に癒合したもの。
[結節間溝]
上腕骨の大結節と小結節および大結節綾と小結節綾の間にある溝状の部分。ここを上腕骨二頭筋長頭の腱が通る。そのため浅部は触知可能だが深部まで触知することは難しい。
[顆間隆起]
脛骨の上関節面のほぼ中央に位置する隆起部。関節内にあるため触知は難しい。
顆間隆起はふたこぶ状に分かれており、それぞれ内側顆間結節と外側顆間結節と呼ばれる。
また顆間隆起の前後の凹部はそれぞれ前顆間区、後顆間区といい、前者には前十字靭帯、後者には後十字靭帯が付着する。
歯突起と顆間隆起は触診不能です。
結節間溝については、間溝内を上腕二頭筋長頭腱が通過し、完全に触知する事は難しいため、問題文により解釈が異なる可能性があります。
例えば、同じ選択肢で、「触診が可能なのはどれか。2つ選べ」だった場合は、胸骨角と舟状骨粗面が選ばれる事になります。
まずは、触診が絶対にできない選択肢と、触診の際の代表(ランドマークなど)とを線引きして、最も正解と思われるものが何を考える必要があります。