Q42 変形性膝関節症の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドライン第1版(日本理学療法士協会)で推奨グレードが最も低いのはどれか。
- 協調運動
- 減量療法
- 有酸素運動
- 筋力増強運動
- ホットパック
※ 下にスクロールしても、
「42 変形性膝関節症の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドライン第1版(日本理学療法士協会)で推奨グレードが最も低いのはどれか。 」
の解答を確認できます。
「Q42 変形性膝関…」の解答
5
スポンサーリンク
正解だった方は、他の問題もどうぞ。
この過去問は、以下の国試の設問の1つです。下のリンク先のページから全問題をご確認いただけます。
この過去問の前後の問題はこちら ▼
ご質問も受け付けています!
「Q42 変形性膝関節症の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドライン第1版(日本理学療法士協会)で推奨グレードが最も低いのはどれか。」こちらの国試問題(過去問)について、疑問はありませんか?
分からない事・あやふやな事はそのままにせず、ちゃんと解決しましょう。以下のフォームから質問する事ができます。「Q42 変形性膝関節症の理学療法……」に関連するページへのリンク依頼フォーム
国試1問あたりに対して、紹介記事は3記事程度を想定しています。問題によっては、リンク依頼フォームを設けていない場合もあります。予めご了承下さい。
更新日:
コメント解説




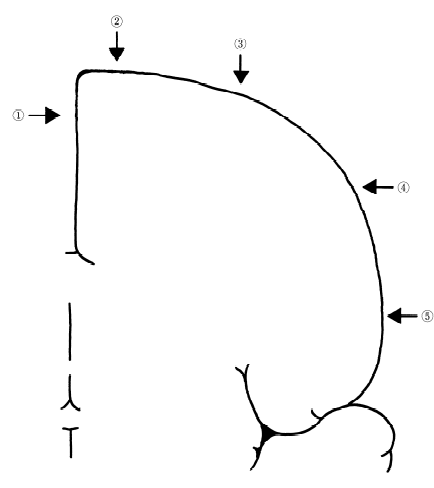
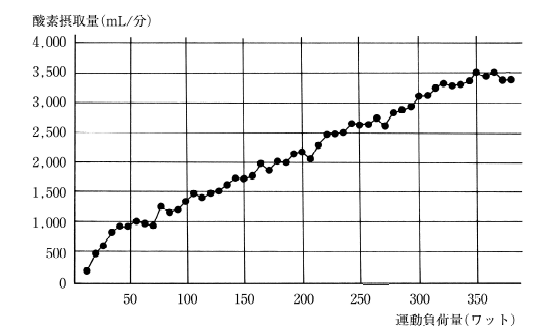
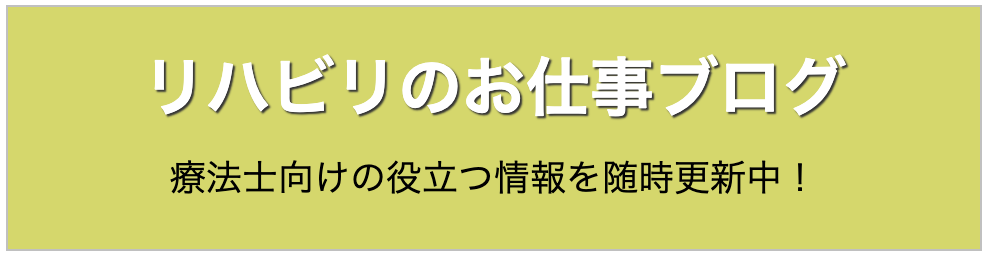


国試問題「第53回理学療法士国試【午前】問42 変形性膝関節症の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドライン第1版(日本理学療法士協会)で推奨グレードが最も低いのはどれか。」について、2件のコメント解説
スポンサーリンク
ホットパック(hot pack)は、「推奨グレードC1」「エビデンスレベル 2」です。
推奨グレードが低いものとしては、以下の通りです。
・ジアテルミー療法群:推奨グレードD エビデンスレベル 2
・非侵襲的神経電気刺激療法:推奨グレードD エビデンスレベル 2
・骨膜刺激療法:推奨グレードD エビデンスレベル 2
膝OAの治療では、グレードの高い介入として、患者教育、減量、運動療法の3つがあげられます。
リハビリテーションなどの保存療法以外では、手術療法として、
「人工股関節置換術【詳細ページ】」
「高位脛骨骨切り術【詳細ページ】」
「人工膝関節単顆置換術【詳細ページ】」
などがあります。
今後、変形性膝関節症のさらに期待される領域としては、再生医療の適応です。
「自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いた変形性膝関節の治療(再生医療)【詳細ページ】」
「PRP(多血小板血漿)療法【詳細ページ】」
などがあります。
しかし、再生医療では、膝に負担のかかったメカニカルな原因(歩容、姿勢、機能障害など)や生活因子などへのアプローチはできないため、再生医療とリハビリテーションを組み合わせた介入が普及すると考えられます。