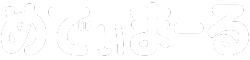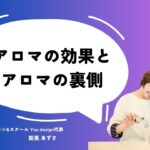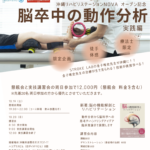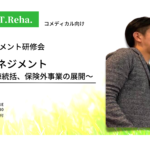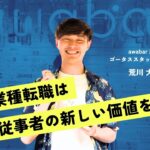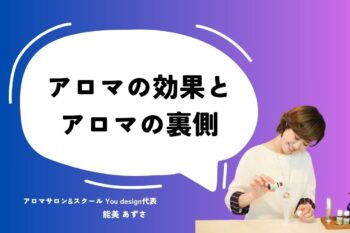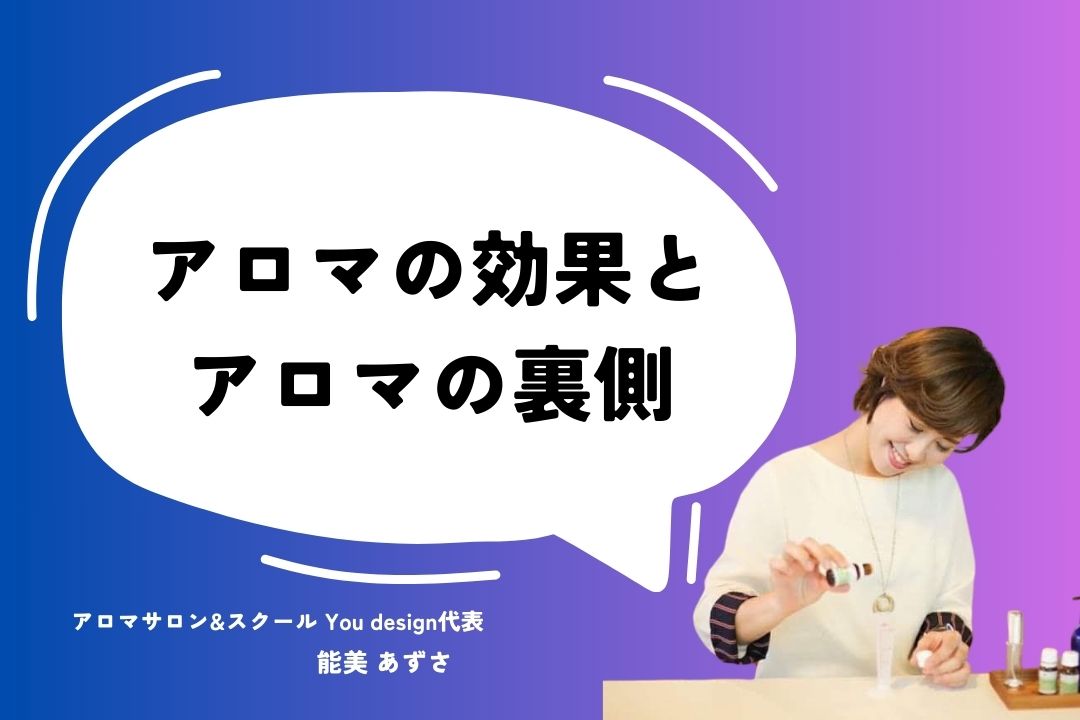
今回はアロマのことを勉強したくて「沖縄でアロマといえば!」ということでアロマサロン&スクール You design代表の能美あずさ さんにお話をお聞きしました!


特に、アロマだけでなく、温活やその他の手技と組み合わせた皮膚塗布による施術は、相乗的な作用でお客様の心身の状態を後押しできていると感じています。
具体的には、
◉忙しさやストレスで生理周期が乱れていた方が、翌日には心身に良い変化があったり
◉2人目不妊で妊活をされていた方が喜びの報告をいただいたり
◉鼻や喉の不快感にお悩みだった方が、呼吸がスムーズに感じられたと喜ばれたり
◉お腹の不調へのアプローチで「かなり体感が得られた」と後日わざわざご連絡をいただく場面も多くあります。
私自身の経験として、産後の後陣痛の際に精油を活用したところ、心地よさを感じて過ごしやすくなったことがあります。
また、出産時には、お産の手助けとなるような精油を活用し、リラックスして陣痛に向き合えるようサポートしました。
精油だけでなく芳香蒸留水や植物オイルなども活用することで、アプローチの幅をさらに広げられると実感しています。


ペパーミントなどは、その特性から3歳未満のお子様や妊婦さんや授乳中の皮膚塗布は推奨されないとされています。
また、一般的に知られているラベンダーやユーカリといった精油も、実は学名によって様々な種類があり、それぞれ成分構成が大きく異なります。
例えば、「ユーカリ」として販売されている精油の多くは「ユーカリ・グロブルス」という学名ですが、これは刺激が強く、お子様への使用は慎重な検討が求められます。
乳幼児への精油の塗布や、大人であっても同じ種類の精油ばかりを長期的に使用するような場合、遅延型アレルギーのリスクを負っているケースも多く散見されます。
さらに、お薬や体質との相性を考慮する必要がある精油も存在します。
例えば、てんかんの既往がある方への使用を避けるべき精油があります。
また、ウィンターグリーンの精油のように、サリチル酸メチルという成分を多く含むため、アスピリンアレルギーをお持ちの方や、血液凝固に影響を与える医薬品を服用している方には、使用に際して専門家の指導が必要なケースなどがあります。

よりメディカルな知識を持つ必要性を感じます。
これもよく危ないって聞くのですが、アロマオイルを“原液のまま”使うと、どう良くないのでしょうか?

アロマオイルは、植物の有効成分が凝縮された非常にパワフルな天然の化学物質です。いかに高品質な精油であっても、その成分が持つ薬理作用、皮膚への刺激性、および体内での作用機序を深く理解せずに原液のまま肌に直接塗布することは、皮膚への刺激やアレルギー反応、光毒性といったリスクを引き起こす可能性があります。
臨床やケアに安全かつ適切に取り入れるためには、表面的な情報に惑わされず、精油のメリットとデメリット、そしてその背景にある科学的根拠を正確に理解し、適切な濃度に希釈して使用することが重要です。


アロマの活用には、決まった活用方法や濃度の基準があるわけではありません。
クライアント一人ひとりの状態や目的に応じて、希釈割合、そして様々な基材や活用方法を判断できる専門的な知識と経験が必要です。

推奨する希釈方法なども今度教えてください!
市販のアロマと、セラピーに使うアロマ精油は別物はやはり全く違いますか?

はい。一般的に市販されている「アロマグッズ」の中には、合成香料や微量の精油で構成されており雑貨品として販売されています。
これらは主に香りを楽しむことを目的としており、必ずしも特定の芳香特性による心身への働きかけを意図していないものも多く存在します。
一方、セラピーに用いる「精油(エッセンシャルオイル)」は、植物から抽出された天然100%の芳香成分です。これらは、その産地、抽出方法、そして成分特性を適切に判断できるよう、分析されているものを選ぶ必要があります。


アロマは、単なる癒やしにとどまらない、専門職としてのケアの幅を広げるパワフルなツールです。ただ、精油の活用には、クライアントさんへの健康被害のリスクを避けるための正しい知識が不可欠です。
「なんとなく」ではなく「意図的に、根拠に基づいて、安全に」活用できるようになるためには、信頼性のない情報に惑わされず、科学的根拠に基づいて精油を選ぶことや、精油成分や作用のメカニズムを理解する必要がある事。
アロマを現在の専門性と掛け合わせる事で、さらに一人ひとりの状態やニーズに合わせたパーソナルなケアが提案できるようになり、クライアントさんの満足度やより良い結果に、さらに貢献できるようになる可能性があるツールである事に気づいてもらいたいです。

アロマのことをセラピストにもっとよく知ってもらえるように、アロマ講座を能美さんにお願いすることができました!
アロマを使いたいのでおすすめの希釈方法なども講座内で聞いていきたいと思います。
この機会に+αの武器をぜひ身につけていきましょう!!

能美あずさ
アロマサロン&スクール You design代表
NARD JAPAN認定アロマ・インストラクターJMF自律神経ケアセラピスト
温灸温活インストラクター/セラピスト
FUFUYA認定リフレクソロジスト
クレイセラピー検定資格
一般社団法人日本プロセラピスト(JPTA)マスター認定講師
一般社団法人日本プロセラピスト協会認定 感動コミュニケーター
一般社団法人ベストライフアカデミーサクセスナビゲーター®